Part1
紀元前
古代エジプト
化粧瓶や手鏡等の化粧道具が数多く発掘され、壁画に化粧をする様子などが描かれている。(A)や(B)で作られた化粧品が発達し、紀元前1930年頃には(C)の通商も盛んだった。
玉座にはスキンケアやフレグランスとして使用された香油をツタンカーメンに塗る王妃の姿が描かれている。また、(D)が入った容器(香油瓶)が見つかっている。
クレオパトラに代表されるように、古代エジプト人のメイクは太く黒いアイライン①とマラカイトのアイシャドウ②だった。
古代ローマ
色白が美しさの基準であり、この頃から入浴が盛んだった。
公衆浴場が点在し、風呂文化が発達していた。身体の汚れを落とすためにオイルを塗り、動物の骨または金属などで作られた肌かき器を使って身を清めていた。
太古上古 (旧石器・縄文・弥生・古墳)時代
日本では外国からの影響をほとんど受けず、原始的な(E)が行われていた。
※古墳から発見された埴輪には男女共に額や頬、首等にこの装飾が見られた。
飛鳥時代
大陸文化と共にシルクロードを通って、西洋文化である鏡や香料、(F)等も日本へ伝わってきた。
宮廷女性の手本も唐の国から伝わった大陸風の物であった。
692年、大陸から渡ってきた僧の観成(がんじょう)によって日本で初めて(F)が作られる。女性天皇である持統天皇に献上したことで大変喜ばれたという記録がある。
奈良時代
日本では、絢爛豪華な大唐朝文化の渡来がますます盛んになった。
化粧品としては(G)などが大陸から日本へ入ってきた。
鳥毛立女屏風(とりげつりつじょのびょうぶ)という正倉院所蔵の宝物に描かれた女性に当時の化粧の特徴③が描かれている。
中国では、唐の時代に文化的な黄金期を迎え、宮廷女官が美しく見えるように化粧技術が発達した。
特に、世界三大美女と呼ばれる(H)は(I)をヘナ(指甲花 : しこうか)で染めていたと言われている。
平安時代
日本独自の文化が発達した。
貴族の住戸(寝殿造)は大きくなり、室内に光があまり入らなかったため、薄暗闇の中でも顔が美しく見えるように顔に白粉を塗り、白さを強調した。
貴族は(J), (K)を原料とした白粉を使い、紅は紅花から作られたものを中心に使っていた。
庶民は(J)を原料とした京白粉や米、粟のでんぷん白粉を使用していた。
男性は忠義の証として、女性は成人した証として(L)が行われていた。また、汗をかかない程高い身分の証として(M)が行われていた。
そして、武士が実験を握るようになると上流武士たちにも(L)と(M)の文化が浸透していった。
問1. 空欄(A)~(D)に入る言葉を答えよ。
問2. 下線部①、②の目的をそれぞれ答えよ。
問3. 空欄(E)に入る言葉を答えよ。また、その目的も答えよ。
問4. 空欄(F)に入る言葉を答えよ。
問5. 空欄(G)には入るものを2つ答えよ。
問6. 下線部③の特徴を答えよ。
問7. 空欄(H)に入る人物を答えよ。また、空欄(I)に入る身体の一部を答えよ。
問8. 空欄(J)と(K)に入る元素をそれぞれ答えよ。
問9. 空欄(L)と(M)に入る言葉を答えよ。
Part1 答え
答えはこちら
問1. A. 水銀, B. タール (順不同), C. 香料, D. 軟膏
問2. ①. 魔よけのため、②目を日差しや虫、感染症から守るため
問3. E. 赤土粉飾
目的 : 魔よけのため
問4. F. 鉛白粉
問5. G. 紅、白粉、朱、香料 のうちのいずれか2つ
問6. 眉が太く、口紅を差している。
問7. H. 楊貴妃, I. 爪
問8. J. Pb(鉛), K. Hg(水銀)
問9. L. お歯黒, M. 眉剃り

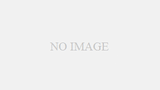
コメント